|
||
●1502年2月10日、ガマは第2回の航海に出発した。この航海で未知のインドサイを、ポルトガルのマヌエル国王(Manuel,o Venturoso 1495ー1521年)のために持ち帰った。 |
||
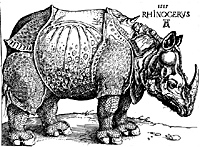 このデューラーの犀のオリジナル画は現在大英博物館にある。このサイは贈り物としてポルトガル王からローマ教皇に送られる途中、運んでいた船が沈没してジェノバ沖に沈没、溺れ死んでしまった。 この事からもデューラーが直接サイを見て描いたわけではない。彼が画に付けた詳細な説明文によれば、彼が古代からの著作に眼をとうしていたことは確かである。何故ならばこのサイは一角サイであるのに、角が二本描かれているからである。デューラーの描いたサイ 拡大表示 |
||
|
||
|
|
||
| |
||
 ●日本にも犀の事は伝わったが写真のように不思議な霊獣として古くから存在した。写真は大田区の神社「久原東部八幡神社」のものであるが、日光東照宮にも同様のすばらしいものである。(西回廊蟇股)詳細は下記の記述を参照。 |
||
●驚くことにこの動物は犀〔サイ)であるという。 |
||