|
||||
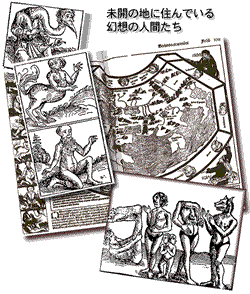 |
 |
■左のイラストは、1493年に出版された『ニュルンベルク年代記』(スケデル)から21種類の化け物。スケデルは生物学好奇心から取り上げている。 |
||
■イラスト拡大表示 1番 2番 3番 |
||||
| ●上、左のイラストは、14世紀にローマ法王の使者として元に赴い た宣教師ジョバンニ・ダ・マリニョリの旅行記 『ボヘミヤ年代記』のもの。『幻想博物誌 』 澁澤達彦著 河出書房刊 | ||||
|
●スキヤポデス(1番のイラスト下から2番目) |
||||
|
|
||||
トップに戻る 第一章 第3章