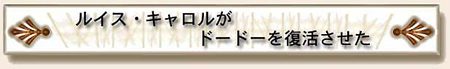 |

『不思議の国のアリス』(原題『Alice's Adventures in Wonderland 』
1865年刊)
皆さんが子供のころに、一度は『不思議の国のアリス』の物語を聞いたり読んだりしたことがあるでしょう。この本の中に、ガチョウに似た不格好な大きな鳥が登場します、それが「ドードー」だったのです。ドードーは空想上の鳥ではなく、インド洋上のモーリシャス諸島に住んでいた実在の絶滅鳥だったのです。
●本はイギリスのルイス・キャロル(Lewis
Carroll) が、小さな女の子「 アリス・リデェル」のために書いた空想物語です、主人公の名前は「アリス」可愛い小さな女の子です。
〈物語の始まり〉
アリスが、ある日チョッキを着た白いウサギのあと追っていくと、突然、地面の穴に落ちてしまいます。
ここから、ワンダーランド(地下)でのアリスと、不思議な虫や動物との空想冒険物語が始まります。ドードーは、アリスが自分の涙で出来た池に落ちてずぶぬれとなり、岸に上がった第三章に登場します。
|

「どうって、あいかわらずびしょびしょしよ」アリスはゆうつそうに、「これじゃ 全然乾きそうにないけど」
「だとすれば、ですね」ドードーが立ち上がって、しかめつらしくいいだした。 「つまり、からだを乾かすためならば、堂々めぐりするのがいちばんじゃないで
しょうか」 みんなは、ヨーイ・ドンで好き勝手なほうに走り出した。
30分程のちにレースは、 突然ドードーの「レース終了」合図で終了する、「みんなにご褒美を」という ドードーの提案で、アリスの持っていたボンボン菓子をくばった。アリスにもごほうびということに、またもやアリスの持っていた「ゆびぬき」を、ドードーがうやうやしくアリスに渡した。アリスも全体に何だかばかげた感じがした。
海洋堂のフィギア「人形の国のアリス」アリスに指輪を渡すドードー
|
 (『不思議の国のアリス』矢川澄子訳 金子国義絵 新潮
社版、平成2年) (『不思議の国のアリス』矢川澄子訳 金子国義絵 新潮
社版、平成2年)
ルイスキャロルの原文はイギリスのアリスのHPにあります、日本でもアリス関連のHPがあります、次のページにリンクがありますので興味のある方はご覧ください
|
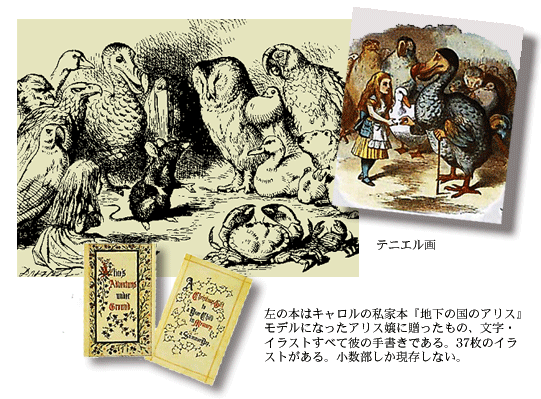
上のイラストはコーカサス・レースの終了後にアリスに指ぬきを渡すドードーの場面。
|
『不思議の国のアリス』のイラストについて……
●モノクロのイラストは、ネズミの話を聞くアリスと動物達、ネズミは長い悲しい話をするが、アリスは良く聞いておらずネズミを怒らせてしまいます。ネズミはアリス達の家庭教師であった「ミス・プリケット」
がモデルであると言われています。
イラストを描いたのはイギリスの「サー・ジョン・テニエル」でした。彼は木口木版の版面に直接下絵を描き彫らせました。はじめは色なしの線描画でしたが、のちにカラーで
輪郭のはっきりした画になり、動物たちの実在感をもたせることに成功しました。(図版『不思議の国のアリス』(株)東京韻書館 1991年 )
●『不思議の国のアリス』は、1865年イギリスのマクミラン社から発行された。その後、世界中で翻訳され愛された、童話版も数多く出版された。
この場面もたくさんの挿し絵が描かれた。また、本の表誌にもドードーが描かれたものが多数存在する。そのためにドードーは世界中で有名になったのである。この物語でドードーは何か的はずれなことを言う「太った愚図な鳥」というイメ
ージで 書かれている。
《では、ルイス・キャロルはどこでドードーを知ったのか》
●その答えは彼の日記にあった。 勤めていたオックスフォード大学に、ドードーの油絵と残された唯一の嘴や骨があったのだ。
そこでアリスと散歩の途中でよく見ていたらしい。いつかこの不思議で哀れな鳥を物語に登場させようと思っていたのだろう。(次のページにオックスフォード大学の写真が有ります)
|
|
 
《ルイス・キャロルはマジック好きだった》
●19世紀末はマジックの大流行であった。良く知られたハリー・フラディーなどの出た時代である。ルイス・キャロルもマジックが大好きであったらしい。彼自身もハンカチを使ったマジックが出来たと言う。
その影響か、『不思議の国のアリス』に登場するウサギは、マジシャンの格好をしている。チェック縞のチョッキ、手には時計を持ちのぞき込んでいる姿など、立派なマジシャンである。その好奇心がこうじて写真を撮ったりしたのではないか。そして晩年には、コナンドイルのように、心霊思想などに興味を示していた。
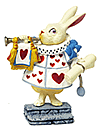
■参照・『キャロル大魔法館』ジョン・フィッシャー著(河出書房新社)、
『世紀末異貌』高山宏著(株)三省堂刊 1990年 を読んでみると参考になります。 |
   |
| トップに戻る
第2章 第3章
|
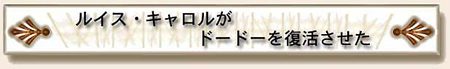

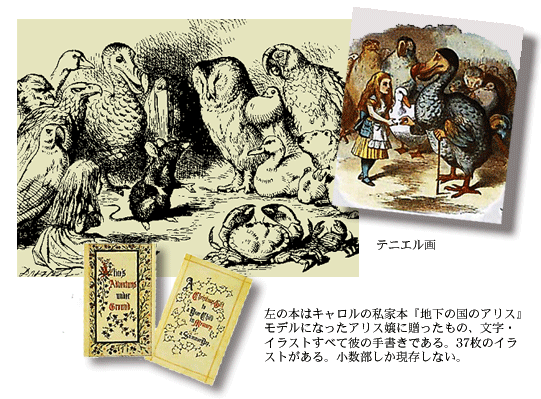

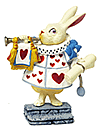
 (『不思議の国のアリス』矢川澄子訳 金子国義絵 新潮
社版、平成2年)
(『不思議の国のアリス』矢川澄子訳 金子国義絵 新潮
社版、平成2年)